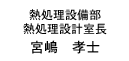|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
| 「今まで誰もやったことのない技術で、世界を席巻したい。」 “技術屋”なら、誰もが1度は抱くそんな思いを、果たしてどれくらいの人が結実させられるだろう。 <クリーンチューブ対応型銅管焼鈍炉>(以下CT焼鈍炉)はその稀有な1例といっていい。開発打診を受けてからわずか3ヶ月という、この分野においては異例に短い期間で成果をあげ、今や“世界標準”になる勢いをみせているのである。 エアコンや冷蔵庫などに使用されている、地球環境に有害なフロンガスを、環境負荷がきわめて少ないクリーンフロンに代替するためになくてはならないクリーンチューブ。その製造のキーテクノロジーである大同のCT焼鈍炉開発の経緯に迫る。 |
||||
|
|
||||
1993年の春、奇妙なことがあった。異なる3社の大手銅管メーカーから、ほぼ時を同じくして同様の開発打診が寄せられたのである。当然大同の営業窓口はそれぞれ異なり、熱処理炉の設計を担当する宮嶋らのもとに話がきたのも、3件バラバラであった。この時宮嶋は、直感的にある“確信”を持った。 “これは世界を席巻するスゴイ開発になるかもしれない・・・。” 工業炉メーカーはどちらかといえば客先から仕様が出てはじめて商談がスタートする、“受身的なビジネス”が大半であった。いいかえれば高度成長期〜バブル期までは、ユーザーからの膨大な引合をいかに効率良く受注できるかが勝負だったのである。そんな中で宮嶋は、自らのビジネス交流や海外で得た経験から、 “これからの時代は技術者といえどもマーケティング<市場戦略>を意識した研究開発が不可欠である” と唱え続けていた。それは時には全くの孤軍奮闘的な主張であったという。 しかし件の3つの開発依頼に、宮嶋は自らの主張を実践する場を得たと予感した。エアコンや冷蔵庫などの環境負荷を低減するための技術の大きな可能性・・・。そこで他の業務の合間を縫って、独自にこの話の背景と市場性を調べてみることにした。技術者宮嶋自らのマーケティングの実現であった。 |
||||
|
|
||||
|
|
||||