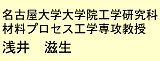|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| しかし浅井氏の話しを聞くにつれ、出向井は“漠然とした勝算”ともいうべき感覚を覚えたという。 数年後、夢の金属といわれたチタンは、一気に商業ベースにのり、ゴルフヘッドをはじめ、量産品向け素材の仲間入りを果たす。・・・その大きな牽引役となったのが、出向井らの開発した“レビキャスト”であった。 今号はチタンの新時代を拓いたこの“レビキャスト”の開発経緯を追ってみる。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
浅井教授(当時は助教授)が海外視察から持ちかえった “コールドクルーシブルレビテーション研究”の話は、大同以外にも教授と交流のあった主だったメーカー、研究機関にももたらされた。しかし教授はこう述懐する。 「結局、商業レベルでの実用化に成功したのは、世界でも大同さんだけですよ。画期的な技術というのは、原理を確立することより、それを実用化することのほうがはるかに大変なことが多いのですが、そういう意味でも、出向井さんの知恵と行動力が生み出した“LEVICAST”は素晴らしい。」 ここまでのくだりでわかるように、大同のLEVICASTの元になっている技術は、コールドクルーシブル型レビテーション溶解法である。レビテーション溶解法というのは、溶解炉の内部で誘導磁場をつくり、これによって対象物を浮遊させながら溶解する技術である。いわば宙に浮かせて溶かすのである。これは、理論的にはチタンの溶解に非常に有効である。チタン(正確にはチタン合金)は融点温度が高い上、ごく微量の不純物が混入するだけで著しく性能特性を損なってしまうやっかいな金属である。従って、溶解工程において、溶けたチタンが炉の壁面のわずかな不純物を“拾って”、性能劣化などの大きな問題となってしまうのだ。そこで宙に浮かせながら溶かす方法が理にかなっているというわけだ。 しかし、いかにチタンが金属の中では比較的軽量とはいえ、されど金属、炉の中で磁力によって浮遊させながら溶かすというのは容易ではない。出向井の学生時代の研究経験からいっても、せいぜい数gの浮遊溶解が限界であった。とても商業レベルで実用化できる分量ではない。 浅井教授の持ちかえった“コールドクルーシブル型・・・”は、これを克服すべく半浮遊状態、つまり溶解した部分だけが浮遊する方式だったのである。 「これならイケル!」出向井は直感した。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
出向井は、浅井教授の話しを開発テーマにすべく、早速大同社内のしかるべき人間に相談を持ちかける。が、反応はよくない。そこで機械、電気、製鋼などの、社内の各スペシャリストを集め、検討会議も回を重ねた。しかしやはり誰も聞く耳を持たない。というより出向井の話すコールドクルーシブルの可能性が全く実感できないといった感じであったらしい。 浅井教授曰く、「電気炉の世界的なスペシャリスト、大同の方々ですらそうなんですから、この技術がいかに当時は机上の空論的な認識でとらえられていたかわかるでしょう。なんせ、誘導磁場を電気で発生させるためには、炉の壁面にたくさん溝が必要で、溶けた2千度近いチタンがそこから漏れる危険性を考えると、とても実用域に相当する容量の炉を開発しようなんて気にはなれなかったんでしょうね。」出向井も、「もしそれなりの量の溶融チタンが漏れたら、大惨事になる危険性だってあるから、もうみんなで反対の大合唱でしたね。」と振りかえる。 しかしここからの出向井の行動は尚素早かった。まず知っている町工場に話しを持ちかけ、浅井教授に技術的指導を仰ぎながら、ごく小さなコールドクルーシブル型溶解炉の実験器をほとんどタダ同然で完成させる。一度の溶解質量はわずか100g程度のものである。 論より証拠で、この実験炉によってどうにか開発行動の社内的な根回しをとりつけると、すかさず学会活動(日本鉄鋼協会電磁冶金研究会)にも積極的に参加し、関連技術の世界的な情報収集に努めた。 さらに、通商産業省工業技術院(当時)の官民連帯共同研究制度にも参画し、それまで難解とされていたチタンの精密鋳造技術の共同開発(他に日産化学工業、富士電機が参画)にも乗り出した。 そんな中で、出向井はある程度の試行錯誤を繰り返しながら、次第にこの開発の実用化への道筋を見出していた。それがコールドクルーシブル型溶解炉と、減圧吸引鋳造法の合体、つまりLEVICASTの原理であった。 |
||||||||||||||