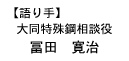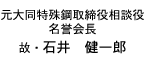|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
石井健一郎。大同の歴史において“中興の祖”と称される人物である。この年石井は、大同製鋼(大同特殊鋼の前身)筆頭取締役就任直後の海外視察の際、目にした欧米諸国の光景に、日本への本格的なモータリゼーションの到来も遠くないと確信し、自動車産業に特殊鋼発展の道を見出した。その石井が、独創的発想力と天才的決断力、そして鋼の如く強い信念により、特殊鋼業界の命運を賭けて挑んだ一大プロジェクト。その結晶が、設立以来現在に至るまで、常に世界の特殊鋼業界をリードしてきた、大同の「知多工場」である。 現在、年間生産量180万トン。その規模、技術力ともに世界でもトップクラスの特殊鋼一貫製造拠点として君臨し続ける大同特殊鋼知多工場。今回のフロンティアDでは、大同の大いなる発展のみならず、特殊鋼の飛躍的な普及をかなえ、業界全体の発展に大きく貢献したこの革新的大工場の歴史と、幾多の試練に立ち向かい、一大プロジェクトを成功に導いた石井の姿を追う。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
石井の、いや大同の運命は敗戦によって大きく路を変えたものと思える。GHQの政策による「財閥解体命令」の余波により、大手各社の主要経営陣は皆一様に職を追われていった。それは、大同においても例外ではなく、当時41才の石井も、気がつけば、自分の上役達は皆いなくなり、会社の実権を握るトップの座が空席となっていた。こうして、成り行き上筆頭取締役に就任した石井であったが、その前途には深い暗雲が立ち込めていた。 戦後、社会基盤が不安定な状態の中、一度は朝鮮戦争特需に沸いた日本であったが、これが終結すると深刻な反動不況に襲われ、大同も業績不振の苦境に立たされていた。 そんな中、石井は大同の、ひいては特殊鋼の新たな進むべき道を求め、海外視察に向かうのだ。そして、たどりついた欧米諸国で、石井はまさに活気づこうとしているモータリゼーションの胎動を感じ取る。石井にとってそれは、救いの光とも取れる眩しい光景であった。そしてこれこそ特殊鋼の生きる道と確信し、自動車産業への特殊鋼供給に照準を合わせた。 自動車部品用の特殊鋼を製造するとなると、いかに効率的な大量生産でコストを抑えることが出来るかが大きな課題となってくる。石井は自社の設備を振り返り、現状の生産体制ではコスト削減は難しく、大幅に規模を拡大した壮大なプラントが必要だと考えるようになった。 向かうべき目標を定めた石井は、持ち前の行動力とこれまでに築き上げた強力なネットワークを駆使し、計画を具体化しようと奔走する。そして程なく、海外視察で見たドイツのエーデルシュタールの工場をモデルとする、大規模な新工場の建設を思い描くようになっていた。その規模は、近い将来の自動車部品用の需要を見据え、”年産50万トン“を想定するもの。これは、当時の国内特殊鋼の総生産量に匹敵する。つまり一工場で、それまでの国内総生産量と同じだけの特殊鋼を作ってしまおうというわけだ。 もちろん、この新工場を実現するためには莫大な投資資金が必要となり、その額はおよそ200億円に達すると見込まれていた。これは当時の大同の年間売上高を上回る数値で、あまりにも現実離れした額であったといえるだろう。石井の描いたプロジェクトは、まずは真っ向から否定される結果となった。しかし石井は決して諦めることはなかった。 「特殊鋼業界に必ずこの規模の生産プラントが必要になる時が来る。今からその準備をはじめるべきだ。」 という確固たる思いを胸に秘め、ひたすらプロジェクトの実現を目指した。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 「もはや大同一社で成し遂げられるプロジェクトではない―。」 この現実に行き当たった石井が次に目指したのは、特殊鋼業界あげての計画遂行であった。石井は早速、新工場建設の構想を携え、他の特殊鋼メーカーを訪ね廻る。来るべき自動車時代に向けて、特殊鋼業界全体の発展を実現させるためにも、かつてない生産量を想定した新工場が必要不可欠であると各社社長に熱心に説いた。 石井の一途な思いは伝わり、各社社長に口頭での了解を得るまでにこぎつけていた。いよいよ計画準備に取り掛かり、万事が順調に進んでいるかのように見えたこの時、しかしながら天は石井に味方してはくれなかったのである。 なんと、このプロジェクトに賛意を示した社長達が、ある者は世を去り、ある者は職を離れて、短期間のうちに石井を残すのみとなってしまったのだ。だが、大同には悲嘆に暮れる時間すら許されてはいなかった。時代は、”神武景気“という戦後初の好景気を迎えようとしていた。世の中では家庭電化製品が三種の神器ともてはやされ、自動車産業においても本格的な乗用車の生産が始まりかけていた。まさに石井が予見した方向に時代は動き出していたのだ。 そのうえ、にわかに慌ただしくなった特殊鋼業界に、高炉一貫メーカーが、意欲的に進出を図りはじめ、大同にとっては新たな脅威となりつつあったのである。こうした状況の中、石井は大同単独での計画遂行を決意せざるをえなくなっていた。
また、製鉄所(現新日鉄)に隣接する工場用地も知多に確保した。これはかつてない莫大な生産量のため、スクラップの調達に瀕した場合にも、製鉄所から溶銑を運び入れるべく意図した立地である。 こうして、苦しいながらも着々と準備を進めていたまさにその時期、大同を未曾有の惨劇が襲うのである。 |
||||||||||