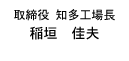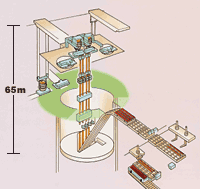|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
大同の連続鋳造の歴史は古い。1972年の一号機(渋川工場)を皮切に、1980年には二号機(知多工場)・三号機(星崎工場)を相次いで設置。特殊鋼の大量生産時代における生産性・効率化の飛躍的な向上に先鞭をつけた。 ただしこれらは現在の普及型である“湾曲型”だった。80年代になると、大同ではさらなる高品質、高効率化を目指し、湾曲型では無し得ない、さらにシビアな成分要求をも満たす“夢の連続鋳造設備”の研究に着手するようになる。 果たして1992年。大同製母材の世界的な名声を、さらに磐石なものに成さしめた『垂直式丸型断面連続鋳造設備』(以下No.2CC)が知多工場に完成する。 設計に取りかかってから完成まで丸3年。この手の設備建設としては異例の長期工事を経て、“夢の連続鋳造設備”は現実のものになったのである。その経緯を一人の開発者を軸に追ってみたい。 |
|||||||||||||||
1989年。No.2CC設置のプロジェクトチームに任命された稲垣らはそううそぶいた。 この時点で、すでに大同の開発チームによって、「No.2CCは垂直式でかつ断面が丸型」という基本構想が描かれていた。この利点は、従来の”湾曲型“に比べ成分偏析の極めて少ない連続鋳造を実現することである。無論稲垣らはこれに反論したわけではない。 ”どうせ造るなら、より効率的で画期的なモノにしたい“というわけだ。この辺り、与えられたテーマの遂行だけでは終わりたくない稲垣らの反骨が見える。 ともあれ、まずプロジェクトチームが取り組むのは実施構想である。とてつもない高温の溶鋼が、垂直に上から下へと流れて行く過程で鋳込まれていくためには、速度と距離の計算が必要であった。あまり早く流れてしまえば、適度な鋳込み具合を得られないし、かといって無制限に設備の全高を伸長することはできない。そうして65m(鋳造部高さ45m)という全高が導き出された。
「制御室が全然違うトコロにあったんじゃ、効率が悪くてしょうがない。両CCの管制作業をできるだけ共有化できれば、凄い効率化になるだろうって思いましてね。それに耐震性にしたって地上高があまり高いのはうまくない。そうなるとNo.2CCは地下に穴を掘って建てるしかないなって。」 こうして両CCの高さを合わせるべく、No.2CCの建設予定地に直径24m、深さ28mの巨大な穴を掘ることになる。全高が高い分、地下に掘り下げ、地上高を合わせようというわけだ。 しかし知多工場は埋立地。この”穴掘り作戦“は後々まで稲垣らに尋常ならざるプレッシャーを与え続けることになるのである。 |
|||||||||||||||
穴掘りはまず、穴の周囲に土留めを張り巡らせることから始まる。巨大な円柱を縦に何十分割したように掘削し、一本ずつコンクリートを流し込んでゆき、最後に円柱上の土留めが完成する。次に少しずつ穴を掘り下げ、掘り下げた分だけコンクリートの内壁で固めていく。ところが掘り進むにつれ海水圧は膨大になっていくのだ。 「下手をすれば、猛烈な水圧で土留めや工事済のコンクリート内壁までもが一瞬にして吹っ飛ぶように浮き上がってしまうかもしれない。そう思うと精神的なプレッシャーで気が気ではありませんでしたね。」 この打開策としては、土留めに沿って無数の井戸が掘られ、海水を汲み上げ、圧力を調整しながらの作業となった。 そうしておよそ1年半。コンクリートの厚い壁で囲まれた直径24m、深さ28mの堂々たる巨大穴が、知多工場に完成するのである。 ちなみにこの穴にかかる浮力は常時約2万2千トン。これだけの圧力に耐え得る設計はなされたものの、万一何かが起きたらという不安は、この後に続く肝心の設備工事の時も、常に稲垣らにプレッシャーを与え続けた。
こうして、稲垣らプロジェクトチーム全員が、思い思いにしたためたメッセージと、当時の新聞などを詰めこんで、アルゴンガスを充填したチタン合金製タイムカプセルが穴底に埋められた。それは恐らく、チームの誰かが生きているうちには再び光を見ることがない遥か未来への贈り物。稲垣らのロマンの結晶である。 |
|||||||||||||||