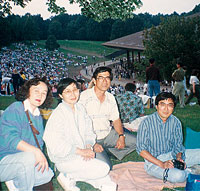|
|
||||||
|
|
||||||
大同では、何をおいても人材育成を、会社を育てるための軸として考えている。では、その“人づくり”のポイントとはどういうものであろうか? まず、前述した特殊鋼の持つ“尊い鋼”としての価値を社員に理解してもらい、仕事に愛着を持ってもらう。そして、グローバルな視点を持った人材の育成。“ヘッドワーク(頭脳)、ハートワーク(精神)、フットワーク(体力)”のバランスの取れた人材の育成。そしてこうした人材が力を十分に発揮できるチーム作りといった点がポイントだと小澤は語る。 これらの条件の一つ一つは、すべて小澤の長年の現場経験で得た実感から生まれたものでもある。 3年間のアメリカ赴任では、経営の建て直しにつながる現場の効率アップや技術力アップの実現を任された。しかし、このアメリカでの生活は小澤にとって“苦難の連続”であった。このとき現場の効率アップを阻んだのは“チームワークの欠如”。 「ひとりひとりの技術力は、日本と比べても決して低くはないんです。ただ、チームワークを重視する姿勢がないからなかなか効率化に繋がらなくて、本当に苦労しました。」 と、小澤は当時を懐かしく振り返る。 ここでの任務は、成功とは言い難い結果となったが、それでも、言葉の壁を越えて現場の人間と心の通ったコミュニケーションが生まれた感動、旅行ではなく腰をすえて海外に住むことで見えてきた、異国の文化や社会…こうしたものの重要性を身をもって体験し、後に社長の席に座る上でも貴重な経験となった。 現場作りの試練を経験した一方で、さらに振り返れば、技術者として若き日に現場で出会った匠の技、幾度となく救われ、大きな仕事も成功に導いたチームの力、こうした記憶が、今も鮮烈に一人の技術者としての小澤の中に息づいている。そしてこの記憶が現場づくり、モノづくり力への熱い想いを今も保たせているのである。 「様々な企業で、製造現場の“改善”によるモノづくり力の強化が叫ばれていますが、大同ももちろん例外ではありません。ただ、時には“改善”ではなく思い切った“改革”が必要。そしてこの改革を厭わない姿勢が大同の開発力の土壌になってきたとも思っています。」
モデル現場で働く社員たちにしてみれば、毎日の業務にプラスαで厄介事を押し付けられたという空気も当初は強かった。しかしながら、小澤の突きつけた高いハードルのおかげで、プロジェクトを実施したモデル現場は、目に見えて“進化”を遂げていったのである。 自分たちの提案によって、設備が整い、仕事の流れが改善され、効率化が成功を遂げる。 “変わっていく”ことを目の当たりにして、各現場はかつてないほどに活気づいていった。 |
||||||
DMKプロジェクト始動から1年以上たった今、そんな声が大同内では聞かれるようになった。 「現場が活気づいて、社員が元気よく変わっていくのを見るなんて、経営者にとって最大の喜びですよ。」 そう語る小澤の笑みは、会社を率いる社長の顔であると同時に、モノづくりの楽しみを伝えることに成功した先輩技術者としての満足の笑みでもあった。 最後に、大同において今後最も進化するポイントは?と問うと、 「“アドバンスト大同人”。最も進化するのは人でしょうね。」 と自信を持って答えた。 大同の未来ビジョンとは、企業としての利益を増幅させるという意味の企業価値にとらわれず、社会に貢献する価値ある商品、真の尊い鋼を生み出す企業への成長であり、それを実現するのは、モノづくりの楽しさとパワーを理解した“進化した”大同人なのである。 |
||||||